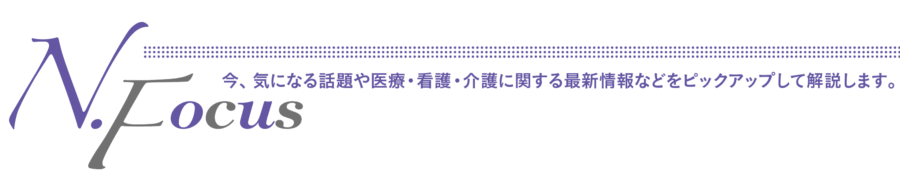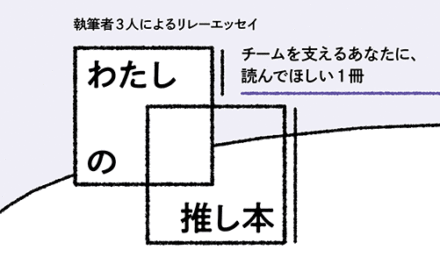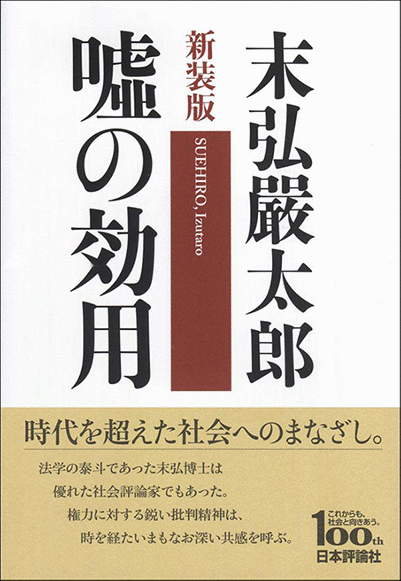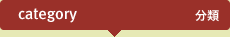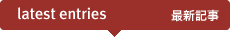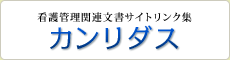看護管理者に必要な知識と視点を網羅したバイブルが
2026年2月に全巻同時改訂!
『看護管理学習テキスト』は、日本看護協会の認定看護管理者教育課程を参照した標準テキストとして2003 年に誕生しました。学習テーマ別に「概要」「論点」「討論」を提示し、問題意識・対応能力の養成につながる構成としている点が特長です。
初版刊行後は毎年、数値データや法律・基準の改正等に伴う記述の更新を行い、認定看護管理者カリキュラム基準の改正に沿うかたちで改訂を重ねてきました。このたび第4 版では、全5 巻で取り扱う「論点」を統廃合し、最新の情報・知見や法制度、社会の動きに基づいて、研究者や現役の看護管理者が実践的に解説しています。
第1巻「保健医療福祉制度・政策論」では、わが国の社会保障制度や保健医療福祉制度の変遷、政策の動向をふまえ、地域のヘルスケアサービスに貢献するために必要な自施設の機能・役割と多組織との連携、看護管理者の役割等のほか、グローバルヘルス政策とその展望等を詳述しています。
第2巻「看護サービスの質管理」では、看護サービスの本質を問いながら、看護の成果や質の保証・改善につながる看護管理の基本的な知識と考え方を紹介。目標管理やBSC といった経営視点から、質評価、患者安全、研究の推進までを体系的に述べています。
第3巻「人材管理論」では、専門職としてのキャリア発達・開発をふまえて、人材育成や教育に関する諸理論を実践に結びつけて解説し、人事システムや賃金制度・体系の知識、労務管理に必須の法律について詳述しています。
第4巻「組織管理論」では、主要理論に基づき、組織の成り立ち・構造、組織分析・開発、組織文化、組織変革、組織倫理を展開。保健医療福祉サービス提供のあり方や、病院組織における看護管理、新興感染症を含む災害管理も解説しています。
第5巻「経営資源管理論」では、経済・経営およびサービス、マーケティングの基本的知識を解説したうえで、組織管理に不可欠なヒト・モノ・カネ・情報を軸に、限られた資源を活用し、効果的・効率的にケアを実践するために必須の知識を整理しています。
別巻「看護管理基本資料集」は、看護に関する基本文書と、看護管理に欠かせない重要法令・公的文書を満載したコンパクトなアーカイブであり、管理業務を法令面からサポートしています。
Data
井部俊子・秋山智弥 監修
日本看護協会出版会(Tel.03-5319-8018)